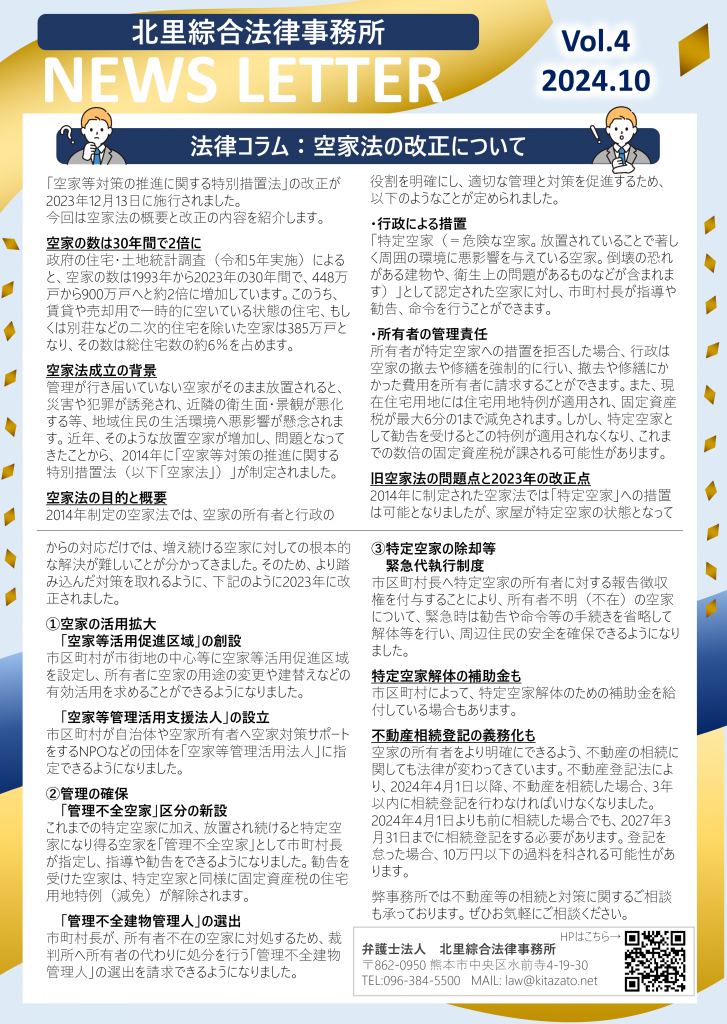「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正が2023年12月13日に施行されました。今回は空家法の概要と改正の内容を紹介します。
・・・
空家の数は年間で2倍に
政府の住宅・土地統計調査(令和5年実施)によると、空家の数は1993年から2023年の30年間で、448万戸から900万戸へと約2倍に増加しています。このうち、賃貸や売却用で一時的に空いている状態の住宅、もしくは別荘などの二次的住宅を除いた空家は385万戸となり、その数は総住宅数の約6%を占めます。
空家法成立の背景
管理が行き届いていない空家がそのまま放置されると、災害や犯罪が誘発され、近隣の衛生面・景観が悪化する等、地域住民の生活環境へ悪影響が懸念されます。近年、そのような放置空家が増加し、問題となってきたことから、 2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)」が制定されました。
空家法の目的と概要
2014年制定の空家法では、空家の所有者と行政の役割を明確にし、適切な管理と対策を促進するため、以下のようなことが定められました。
・行政による措置
「特定空家(=危険な空家。放置されていることで著しく周囲の環境に悪影響を与えている空家。倒壊の恐れがある建物や、衛生上の問題があるものなどが含まれます)」として認定された空家に対し、市町村長が指導や勧告、命令を行うことができます。
・所有者の管理責任
所有者が特定空家への措置を拒否した場合、行政は空家の撤去や修繕を強制的に行い、撤去や修繕にかかった費用を所有者に請求することができます。また、現在住宅用地には住宅用地特例が適用され、固定資産税が最大6分の1まで減免されます。しかし、特定空家として勧告を受けるとこの特例が適用されなくなり、これまでの数倍の固定資産税が課される可能性があります。
旧空家法の問題点と2023年の改正点
2014年に制定された空家法では「特定空家」への措置は可能となりましたが、家屋が特定空家の状態となってからの対応だけでは、増え続ける空家に対しての根本的な解決が難しいことが分かってきました。そのため、より踏み込んだ対策を取れるように、下記のように2023年に改正されました。
①空家の活用拡大
「空家等活用促進区域」の創設
市区町村が市街地の中心等に空家等活用促進区域を設定し、所有者に空家の用途の変更や建替えなどの有効活用を求めることができるようになりました。
「空家等管理活用支援法人」の設立
市区町村が自治体や空家所有者へ空家対策サポートをするNPOなどの団体を「空家等管理活用法人」に指定できるようになりました。
②管理の確保
「管理不全空家」区分の新設
これまでの特定空家に加え、放置され続けると特定空家になり得る空家を「管理不全空家」として市町村長が指定し、指導や勧告をできるようになりました。勧告を受けた空家は、特定空家と同様に固定資産税の住宅用地特例(減免)が解除されます。
「管理不全建物管理人」の選出
市町村長が、所有者不在の空家に対処するため、裁判所へ所有者の代わりに処分を行う「管理不全建物管理人」の選出を請求できるようになりました。
③特定空家の除却等
緊急代執行制度
市区町村長へ特定空家の所有者に対する報告徴収権を付与することにより、所有者不明(不在)の空家について、緊急時は勧告や命令等の手続きを省略して解体等を行い、周辺住民の安全を確保できるようになりました。
特定空家解体の補助金も
市区町村によって、特定空家解体のための補助金を給付している場合もあります。
不動産相続登記の義務化も
空家の所有者をより明確にできるよう、不動産の相続に関しても法律が変わってきています。不動産登記法により、2024年4月1日以降、不動産を相続した場合、3年以内に相続登記を行わなければいけなくなりました。2024年4月1日よりも前に相続した場合でも、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。登記を怠った場合、10万円以下の過料を科される可能性があります。
弊事務所では不動産等の相続と対策に関するご相談も承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
・・・
■ニュースレター版はこちら








 お問合せフォーム ≫
お問合せフォーム ≫