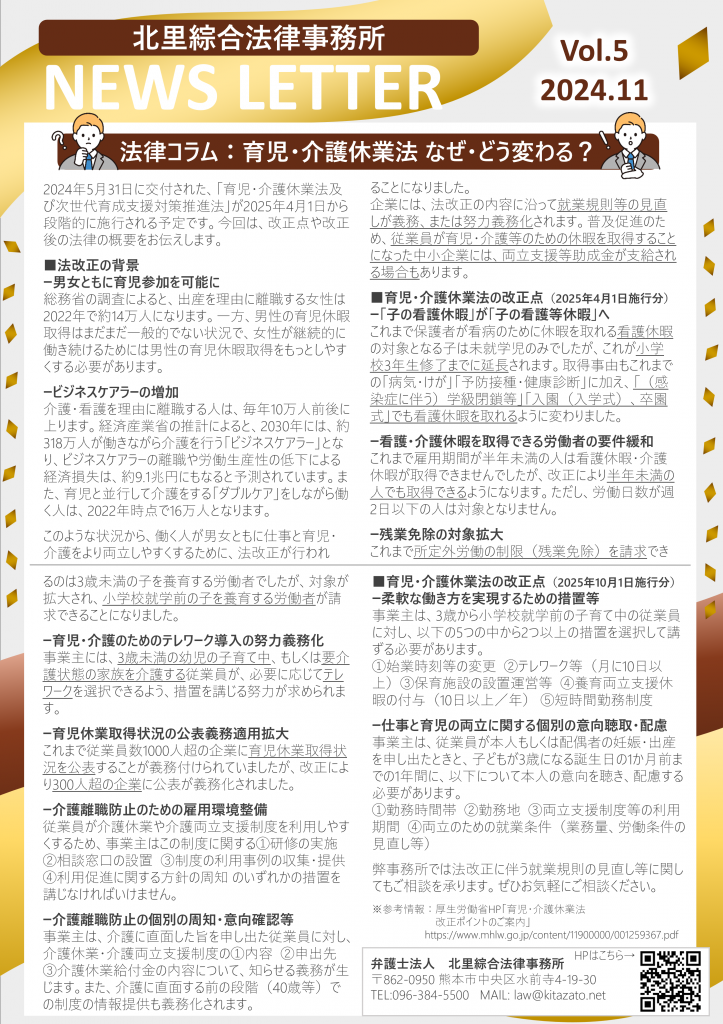2024年5月31日に交付された、「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法」が2025年4月1日から段階的に施行される予定です。今回は、改正点や改正後の法律の概要をお伝えします。
・・・
■法改正の背景
―男女ともに育児参加を可能に
総務省の調査によると、出産を理由に離職する女性は2022年で約14万人になります。一方、男性の育児休暇取得はまだまだ一般的でない状況で、女性が継続的に働き続けるためには男性の育児休暇取得をもっとしやすくする必要があります。
―ビジネスケアラーの増加
介護・看護を理由に離職する人は、毎年10万人前後に上ります。経済産業省の推計によると、2030年には、約318万人が働きながら介護を行う「ビジネスケアラー」となり、ビジネスケアラーの離職や労働生産性の低下による経済損失は、約9.1兆円にもなると予測されています。また、育児と並行して介護をする「ダブルケア」をしながら働く人は、2022年時点で16万人となります。
このような状況から、働く人が男女ともに仕事と育児・介護をより両立しやすくするために、法改正が行われることになりました。
企業には、法改正の内容に沿って就業規則等の見直しが義務、または努力義務化されます。普及促進のため、従業員が育児・介護等のための休暇を取得することになった中小企業には、両立支援等助成金が支給される場合もあります。
■育児・介護休業法の改正点(2025年4月1日施行分)
―「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」へ
これまで保護者が看病のために休暇を取れる看護休暇の対象となる子は未就学児のみでしたが、これが小学校3年生修了までに延長されます。取得事由もこれまでの「病気・けが」「予防接種・健康診断」に加え、「(感染症に伴う)学級閉鎖等」「入園(入学式)、卒園式」でも看護休暇を取れるように変わりました。
―看護・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
これまで雇用期間が半年未満の人は看護休暇・介護休暇が取得できませんでしたが、改正により半年未満の人でも取得できるようになります。ただし、労働日数が週2日以下の人は対象となりません。
―残業免除の対象拡大
これまで所定外労働の制限(残業免除)を請求できるのは3歳未満の子を養育する労働者でしたが、対象が拡大され、小学校就学前の子を養育する労働者が請求できることになりました。
―育児・介護のためのテレワーク導入の努力義務化
事業主には、3歳未満の幼児の子育て中、もしくは要介護状態の家族を介護する従業員が、必要に応じてテレワークを選択できるよう、措置を講じる努力が求められます。
―育児休業取得状況の公表義務適用拡大
これまで従業員数1000人超の企業に育児休業取得状況を公表することが義務付けられていましたが、改正により300人超の企業に公表が義務化されました。
―介護離職防止のための雇用環境整備
従業員が介護休業や介護両立支援制度を利用しやすくするため、事業主はこの制度に関する①研修の実施②相談窓口の設置 ③制度の利用事例の収集・提供④利用促進に関する方針の周知 のいずれかの措置を講じなければいけません。
―介護離職防止の個別の周知・意向確認等
事業主は、介護に直面した旨を申し出た従業員に対し、介護休業・介護両立支援制度の①内容 ②申出先 ③介護休業給付金の内容について、知らせる義務が生じます。また、介護に直面する前の段階(40歳等)での制度の情報提供も義務化されます。
■育児・介護休業法の改正点(2025年10月1日施行分)
―柔軟な働き方を実現するための措置等
事業主は、3歳から小学校就学前の子育て中の従業員に対し、以下の5つの中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
①始業時刻等の変更 ②テレワーク等(月に10日以上)③保育施設の設置運営等 ④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年) ⑤短時間勤務制度
―仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
事業主は、従業員が本人もしくは配偶者の妊娠・出産を申し出たときと、子どもが3歳になる誕生日の1か月前までの1年間に、以下について本人の意向を聴き、配慮する必要があります。
①勤務時間帯 ②勤務地 ③両立支援制度等の利用期間 ④両立のための就業条件(業務量、労働条件の見直し等)
弊事務所では法改正に伴う就業規則の見直し等に関してもご相談を承ります。ぜひお気軽にご相談ください。
※参考情報:厚生労働省HP「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
・・・
■ニュースレター版はこちら








 お問合せフォーム ≫
お問合せフォーム ≫