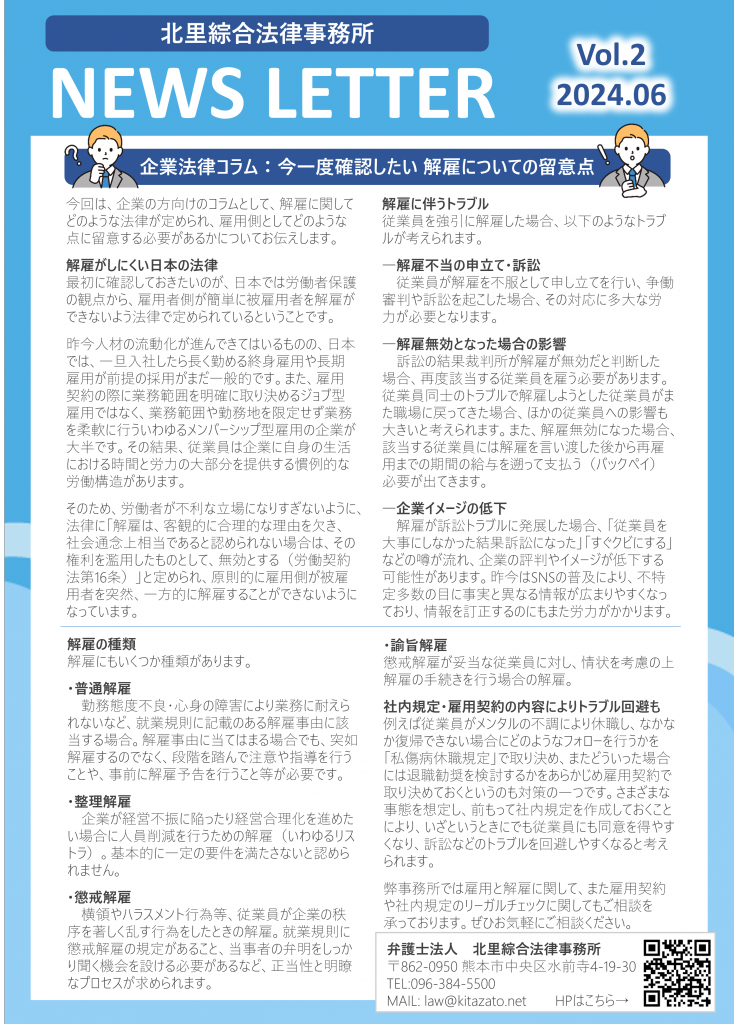今回は、企業の方向けのコラムとして、解雇に関してどのような法律が定められ、雇用側としてどのような点に留意する必要があるかについてお伝えします。
解雇がしにくい日本の法律
最初に確認しておきたいのが、日本では労働者保護の観点から、雇用者側が簡単に被雇用者を解雇ができないよう法律で定められているということです。
昨今人材の流動化が進んできてはいるものの、日本では、一旦入社したら長く勤める終身雇用や長期雇用が前提の採用がまだ一般的です。また、雇用契約の際に業務範囲を明確に取り決めるジョブ型雇用ではなく、業務範囲や勤務地を限定せず業務を柔軟に行ういわゆるメンバーシップ型雇用の企業が大半です。その結果、従業員は企業に自身の生活における時間と労力の大部分を提供する慣例的な労働構造があります。
そのため、労働者が不利な立場になりすぎないように、法律に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法第16条)」と定められ、原則的に雇用側が被雇用者を突然、一方的に解雇することができないようになっています。
解雇に伴うトラブル
従業員を強引に解雇した場合、以下のようなトラブルが考えられます。
―解雇不当の申立て・訴訟
従業員が解雇を不服として申し立てを行い、争働審判や訴訟を起こした場合、その対応に多大な労力が必要となります。
―解雇無効となった場合の影響
訴訟の結果裁判所が解雇が無効だと判断した場合、再度該当する従業員を雇う必要があります。
従業員同士のトラブルで解雇しようとした従業員がまた職場に戻ってきた場合、ほかの従業員への影響も大きいと考えられます。また、解雇無効になった場合、該当する従業員には解雇を言い渡した後から再雇用までの期間の給与を遡って支払う(バックペイ)必要が出てきます。
―企業イメージの低下
解雇が訴訟トラブルに発展した場合、「従業員を大事にしなかった結果訴訟になった」「すぐクビにする」などの噂が流れ、企業の評判やイメージが低下する可能性があります。昨今はSNSの普及により、不特定多数の目に事実と異なる情報が広まりやすくなっており、情報を訂正するのにもまた労力がかかります。
解雇の種類
解雇にもいくつか種類があります。
・普通解雇
勤務態度不良・心身の障害により業務に耐えられないなど、就業規則に記載のある解雇事由に該当する場合。解雇事由に当てはまる場合でも、突如解雇するのでなく、段階を踏んで注意や指導を行うことや、事前に解雇予告を行うこと等が必要です。
・整理解雇
企業が経営不振に陥ったり経営合理化を進めたい場合に人員削減を行うための解雇(いわゆるリストラ)。基本的に一定の要件を満たさないと認められません。
・懲戒解雇
横領やハラスメント行為等、従業員が企業の秩序を著しく乱す行為をしたときの解雇。就業規則に懲戒解雇の規定があること、当事者の弁明をしっかり聞く機会を設ける必要があるなど、正当性と明瞭なプロセスが求められます。
・諭旨解雇
懲戒解雇が妥当な従業員に対し、情状を考慮の上解雇の手続きを行う場合の解雇。
社内規定・雇用契約の内容によりトラブル回避も
例えば従業員がメンタルの不調により休職し、なかなか復帰できない場合にどのようなフォローを行うかを「私傷病休職規定」で取り決め、またどういった場合には退職勧奨を検討するかをあらかじめ雇用契約で取り決めておくというのも対策の一つです。さまざまな事態を想定し、前もって社内規定を作成しておくことにより、いざというときにでも従業員にも同意を得やすくなり、従業員・企業双方の負担を減らすことができます。また、訴訟などのトラブルも回避しやすくなると考えられます。
弊事務所では雇用と解雇に関して、また雇用契約や社内規定のリーガルチェックに関してもご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
・・・
ニュースレター版はこちら








 お問合せフォーム ≫
お問合せフォーム ≫