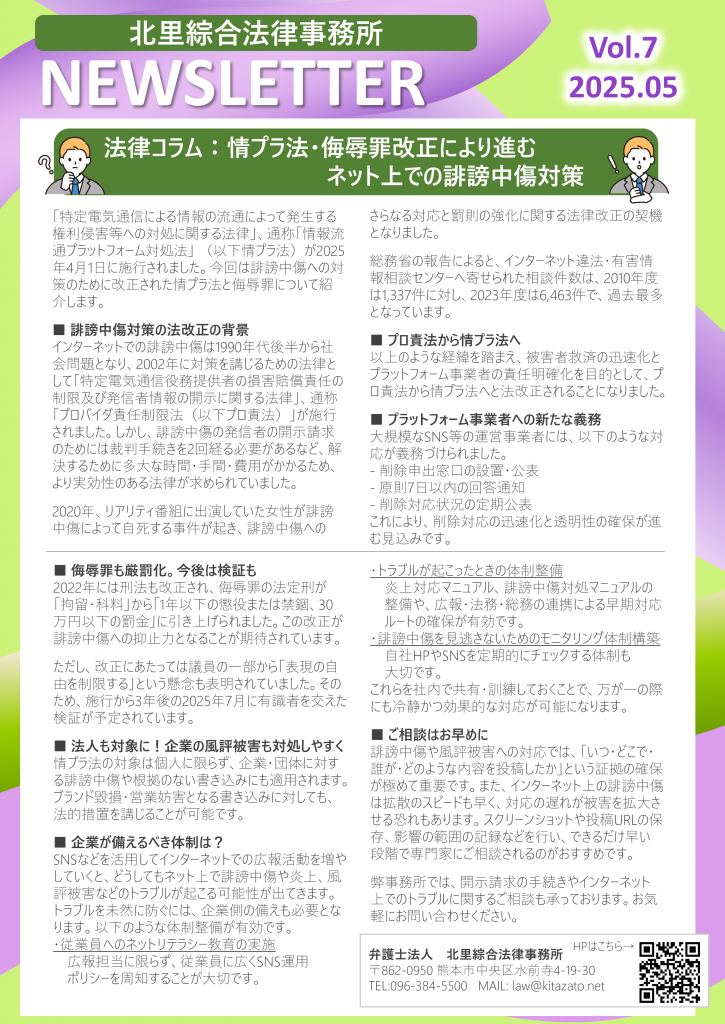「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」、通称「情報流通プラットフォーム対処法」 (以下情プラ法)が2025年4月1日に施行されました。今回は誹謗中傷への対策のために改正された情プラ法と侮辱罪について紹介します。
誹謗中傷対策の法改正の背景
インターネットでの誹謗中傷は1990年代後半から社会問題となり、2002年に対策を講じるための法律として「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」、通称「プロバイダ責任制限法(以下プロ責法)」が施行されました。しかし、誹謗中傷の発信者の開示請求のためには裁判手続きを2回経る必要があるなど、解決するために多大な時間・手間・費用がかかるため、より実効性のある法律が求められていました。
2020年、リアリティ番組に出演していた女性が誹謗中傷によって自死する事件が起き、誹謗中傷へのさらなる対応と罰則の強化に関する法律改正の契機となりました。
総務省の報告によると、インターネット違法・有害情報相談センターへ寄せられた相談件数は、2010年度は1,337件に対し、2023年度は6,463件で、過去最多となっています。
プロ責法から情プラ法へ
以上のような経緯を踏まえ、被害者救済の迅速化とプラットフォーム事業者の責任明確化を目的として、プロ責法から情プラ法へと法改正されることになりました。
プラットフォーム事業者への新たな義務
大規模なSNS等の運営事業者には、以下のような対応が義務づけられました。
・削除申出窓口の設置・公表
・原則7日以内の回答通知
・削除対応状況の定期公表
これにより、削除対応の迅速化と透明性の確保が進む見込みです。
侮辱罪も厳罰化 今後は検証も
2022年には刑法も改正され、侮辱罪の法定刑が「拘留・科料」から「1年以下の懲役または禁錮、30万円以下の罰金」に引き上げられました。この改正が誹謗中傷への抑止力となることが期待されています。
ただし、改正にあたっては議員の一部から「表現の自由を制限する」という懸念も表明されていました。そのため、施行から3年後の2025年7月に有識者を交えた検証が予定されています。
法人も対象に!企業の風評被害も対処しやすく
情プラ法の対象は個人に限らず、企業・団体に対する誹謗中傷や根拠のない書き込みにも適用されます。 ブランド毀損・営業妨害となる書き込みに対しても、法的措置を講じることが可能です。
企業が備えるべき体制は?
SNSなどを活用してインターネットでの広報活動を増やしていくと、どうしてもネット上で誹謗中傷や炎上、風評被害などのトラブルが起こる可能性が出てきます。トラブルを未然に防ぐには、企業側の備えも必要となります。以下のような体制整備が有効です。
・従業員へのネットリテラシー教育の実施
広報担当に限らず、従業員に広くSNS運用ポリシーを周知することが大切です。
・トラブルが起こったときの体制整備
炎上対応マニュアル、誹謗中傷対処マニュアルの整備や、広報・法務・総務の連携による早期対応ルートの確保が有効です。
・誹謗中傷を見逃さないためのモニタリング体制構築
自社HPやSNSを定期的にチェックする体制も大切です。
これらを社内で共有・訓練しておくことで、万が一の際にも冷静かつ効果的な対応が可能になります。
ご相談はお早めに
誹謗中傷や風評被害への対応では、「いつ・どこで・誰が・どのような内容を投稿したか」という証拠の確保が極めて重要です。また、インターネット上の誹謗中傷は拡散のスピードも早く、対応の遅れが被害を拡大させる恐れもあります。スクリーンショットや投稿URLの保存、影響の範囲の記録などを行い、できるだけ早い段階で専門家にご相談されるのがおすすめです。
弊事務所では、開示請求の手続きやインターネット上でのトラブルに関するご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
・・・
■ニュースレター版はこちら








 お問合せフォーム ≫
お問合せフォーム ≫